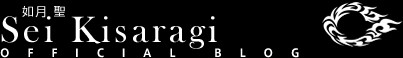文化の中の居心地悪さ
とかく人間は物事を測るのに誤った尺度をもってし、権力や成功となれば自らも得ようと努め、他人でそれに浴する人があれば褒めそやす一方、こと人生の真の価値についてはおろそかにしかちだ、との印象を禁じ得ない。とはいえ、その手の大局的な判断に立つ時、人はつい、人間関係とその精神生活が千差万別であるのを忘れてしまう危険がある。
個々の人物の中には、その偉大さが、世間の大方の目標や理想からおよそかけ離れた特性や功績に基づくにもかかわらず、同時代の人々から尊敬を寄せられる人たちもいる。ややもするとわれわれは、こうした偉大な人物を承認するのは極わずかの者でしかなく、大多数の者は彼らに目もくれないと想定したくなるようだ。
ところが、人間の考えと行いとの間にある不一致や、欲望の轟きも多種多様であるおかげで、話はそう単純にすまないかもしれない。
この類いの卓越した人物の一人が、手紙の中で自分のことを私の友人と称してくれている。私が彼に、宗教は錯覚だと論じた小著を送ったところ、彼は、宗教に関するあなたの判断には全面的に納得するが、あなたが宗教性の本来の源泉を適切に評価していらっしゃらないのは残念だ、とする返信を寄こした。
いわく、この源泉は、自分の思いを決して去ることのできない特別な感情であり、自分の知る範囲でも、他の多くの人々が同様の感情を持つと述べている。おそらく幾百万の人々にその感情があると決めてかかってよいのではないか。
これは、自分が永遠性の感覚と名付けたい感情であり、何か無窮のもの、広大無辺のもの、いわば大洋的という感情なのだ。
この感情は純粋に主観的な事実であり、教養などではない。これがあるといって、当人の死後の永生が保障されるわけではないが、各種の教会や宗教体系もこれを宗教的なエネルギーの源泉と捉えて、それぞれ特定の回路に引き入れ、また当然それを吸収している。
いかなる信仰も錯覚も拒むにせよ、このような大洋的な感情さえあれば、それだけを根拠に、人は宗教的だと名乗ってよい…。
かつて錯覚に備わる魔力を自ら詩情豊かに描いてみせた尊敬する友人のこの言葉に、私は少なからぬ困惑を覚えた。私自身はこの大洋に感情なるものを自分の中に見出すことができない。感情を学問的に論じるとなると一筋縄ではいかない。個々の感情が示す生理学的な兆候を記述しようと試みることはできる。
しかし、これがあまり功を奏さないとなると私は大洋感情なるものもそうした特徴づけでは捉えられそうにないと危惧する、この感情に関して最初に連想として思いつく表象内容に頼るほかない。
友人の述べるところを私が正しく理解しているなら、彼は、一人の奇抜で相当に異端の作家が、自ら死を選ぶのを前にした作中の主人公に慰めとして与えられた俺たちにはこの世界から転げ落ちようがないという言葉と同じことを考えている。
要するに、外界全体と解きがたく結ばれているという感情、一体感である。私にとっては、これはむしろ知的な洞察としての性格を持つものだと言いたい。
もとより感情の色調がそれに伴わないわけではないが、これほどの射殺を持つものは他の似た者についても当然、言えるところであろう。私自身に即して言えば、そうした感情が本性上第一主義的なものだとは確信できそうにない。
だからといって、そういった感情が他の人には事実として生じるというのを否定してはなるまい。ただ、ここで問われるのは、それが正しく解釈されているか、あらゆる宗教的欲求の源泉および起源であると認められるべきか否かである。
こうした問題の解決に決定的な影響を与えるようなことを、私は何一つ述べることができない。
人間は、自分が廻りの世界と一つに連なっており、それは専用の直接的な感情によって分かるはずだという発想は、いかにも突飛でわれわれの心理学の体系構成にうまく収まらないので、一つそうした感情が生じる所以を精神分析によって導出することが試みられてよいだろう。
これには、さしあたり次のような考え方の筋道があると想定される。この自我は自立的、統一的で、他の全てのものから鮮やかに際立っていると映る。
一見もっともらしく思えるのだが、これが誤りであること、自我は明確な境界もないまま内に向かって、われわれがエスと呼ぶ無意識的な心的存在の中へ続いており、自我はこのエスを飾るいわば上辺の装いにすぎないこと、これは精神分析的な研究が初めて説いたところである。
自我のエスに対する関係について、われわれは、精神分析学にもっと多くのことを明らかにしてもらわなくてはいけない。
もっとも、少なくとも外に対しては自我も、明確で鮮やかな境界線を主張しているかに見える。事情が異なるのは、ある一つの状態についてだけである。
これは普通の状態ではないが、さりとて病的と断じることもできない。恋のほれこみが昂じてくると、自我と対象との境界が今にも消失しそうになる。五感からしてそうでないと分かっていながら、恋する者は自分と相手とが一体だと主張し、本当にそうであるかのように振る舞うのを辞さない。
生理的機能によって一時的に停止されることがあるものは、当然、病的過程によって障害を受けたりもするはずだ。病理学からは、自我の外界の境界が不確かになったり、境界が実際に正しく引かれなくなったりする状態が数多くあることが知られる。自分の身体の各部分だけではなく、自分の心の生活、知覚、思考、感情の個々の部分が何か疎遠で、自我に属さないように映る事例もあれば、他方で、明らかに自我の中で生じ自我が認知するべきはずのものを、外界に押し付ける事例もある。要するに、自我感情も様々な障害をきたし、自我の境界は安定したものではないのだ。
さらに考えてみると、成人のこうした自我感情は、当初からそのようなものであったはずのないことが分かる。自我感情は一つの発展を経て出来上がったものであるに違いなく、この経緯は納得のいくように立証はできなくても、まずはこうであったはずとしてかなりの確度で構成してみることができる。
乳児はまだ自分の自我を、自分の中に流入してくる感覚の源泉としての外界から区別していない。様々な刺激を受けて、この区別を徐々に学んでいく。刺激による興奮を与えてくれる源泉のうち、そのいくつかは彼がのちにそれらを自分の身体器官として認識することになるものであり、これらが彼にいつでも感覚を送り届けてくれるのに対して、他方、何よりほしい母の乳房も含め、ときおり彼から遠ざかり、助けを呼ぶ泣き声を立てないかぎり引き寄せられない感覚源泉もあるいう事実は、乳児に非常に強い印象を与えるに違いない。こうして初めて自我に向かいあうかたちで対象が、外にあるものとして、ある特段の活動によって初めて出現させうるものとして立ち上がってくる。
さらに多種多様な痛みや不快の感覚が頻繁に襲ってくるのが避けられず、これが自我を感覚の塊から分離させるべく、つまりひとつの外、一つの外界を認知するべく駆り立て、快原理の無制限な支配を停止させ回避するように命じる。
そうした不快の源泉となりうるものを全て自我から遠ざけ、外へ投げ捨て、一つの純粋な快自我を形成しようとする傾向が生じる。この自我に、自分とは異質の怖い外部が対峙することになる。
この原始的な快自我の境界線は、経験による訂正を免れえない。快の恵みをもたらすものとして破棄したくないもののうちのいくつかは、自我ではなく対象であり、追い出したい苦痛のいくつかは、自我の内に由来し、自我から切離しえないことが明らかになる。感官活動を、意図的な操作と適切な筋肉活動とによって、内的なもの、自我に属するものと、外的なもの、外界に由来するものとを区別すべを学び、これをもって人は、その後の発達を支配することになる現実原理の投入に向けた最初の一歩を踏み出す。もちろんこの区別は、不快感が感知されたり、それが迫ったりしている場合、それに対して自分を防御するという実際的な意図に資するものである。
自我が、自分の内部から来るある種の不快の興奮から自ら防御するのに用いる方法が、外から来る不快に対して使用する方法と別のものではないという事実が、やがて重大な病的障害の出発点になる。
続く。