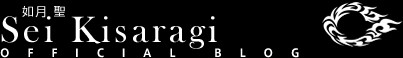フロイトより抜粋。自慰についての討論の閉会の辞
諸君!このサークルの比較的古いメンバーは覚えていることでしょうが、われわれはすでに数年間前、自慰をテーマに同じような共同討論、アメリカの同士の言い方では、シンポジオンをやろうと試みたことがあります。その折には、表明された意見にかなりの食い違いが出來し、そのため、われわれは討議を上梓するまでに至りませんでした。
それ以来われわれは前回と同じ人々も新たに加わった人々も経験的事実を絶えず参照し、お互いの考えのやり取りを継続しながら、自分の見方を明確にするとともに共通の地盤に据えることができるようになり、いまや前回中断されたことを敢行しなおしてもよいだろうと考えられるようになりました。
実際わたしは、自慰のテーマに関するわれわれの一致はいまやその他の点においては否認すべくもない、不一致よりも強力で透徹したものとなったという印象を得ています。矛盾もあるように見えますが、そのかなりは、諸君が展開した観点の多様性によって呼び起こされたにすぎず、問題となっているのは真実のところ、互いに十分並存できる見方なのです。
われわれが一致もしくは不一致になっていると思われるのはどういう点についてなのか、諸君に要約を開示させていただきたいと思います。
おそらくわれわれを全員が一致しているのは以下の点です。
a、 自慰行為に伴うか、それの代役となる空想の意義について。
b、 その由来はどうであれ、自慰につながっている罪責意識について。
c、 自慰の有害性について質的な条件を提示することは不可能であるということについて(この点は例外なく一致しているわけではない)
調停ができなかった意見の相違が示されたのは、
a、 自慰が身体的要因に影響を及ぼすとは認められないということに関して。
b、 自慰の有害性一般の拒絶に関して。
c、 罪責感の由来に関して。これを諸君の一部は不満足から直接指導しようとし、他の諸君は社会的要因や人格のその都度の態度も引き合いに出そうとする。
d、 子供の自慰の遍在性に関して。
最後に重要な不確定性として残っているのは、
a、 自慰に有害な影響があるとして、その影響の規制について。
b、 自慰の現勢神経症への病因論的なかかわりについて。
基づいて行った批判によって問題設定がなされています。たしかにわれわれは、将来の観察者や研究者の人々に、まだ確定し解明すべきことを大量に残しましたが、それでわが身を慰めようではありませんか。
ところで、われわれが取り組んでいる問いに対するわたし自身の寄与に関して、諸君は多くを期待してはなりません。諸君のご存じのように、わたしはテーマを断片的に取り扱うkとを偏愛しており、そうすることで、もっとも確実と思われる点を浮き彫りにしたいのですわたしには、何か新たなことや解決を与えることはできません。ただ、かつて一度主張したことを幾つか繰り返し、またこうした昔からの意見を表明すると諸君の側からなされることになる攻撃に対していくらかの防御をなし、さらに、諸君の講演に浮かんで来ずにはいられなかったコメントを少々付け加えるだけです。
ご存じのように、わたしは自慰を年齢にしたがって、一、乳児の自慰(それによって理解されているのは、性的満足に役立つあらゆる自体性愛的な試みのことです)、二、幼児の自慰(これは第一のものから直接的に出てきますが、すでに特定の性源域に固着されています)、三、思春期の自慰(これは幼児期の自慰に接続しているが、そうでなければ潜伏期によってそれから隔てられています)に区別しました。わたしが伺った諸君の叙述のいくつかにおいては、時期のこの区別は全面的に正しいとはされていませんでした。医学の語法に示唆される、いわゆる自慰の単一性に誘われて一般論的な主張がいくらかなされましたが、むしろあの三時期によって分化する方がより正当なはずでした。
女性の自慰に男性のそれと同じほど顧慮を払うことができなかったのも残念でした。女性の自慰は別立ての研究に値するのであって、まさに女性の自慰おいてこそ年齢によって条件付けられる変化が大変強調されるのではないか、とわたしは考えています。
それでは、乳児に自慰がいたるところで見られることに対する私の目的論的な論拠に反対してライトラーが繰り出した異論の方に移ることにしましょう。告白しますが、わたしはこの論拠を破棄します。性理論の新版が出されることになれば、そこには論難はもはや含まれないでしょう。私は自然の意図を推し量ることなど断念し、事態の記述に徹することになるでしょう。
人間のみに固有な、性器の一定の機構は子供時代における性交渉の阻止を目指しているように思われるという、ライトラーのコメントも意味深く重大だと宣言せざるをえません。けれど、私の懸念はこん点に関してなのです。
女性器の窪みが閉鎖され、勃起を確実にするペニスの骨が脱落したことは、性交それ自身の妨げになるだけであって、性的興奮一般の妨げとなるわけではないのです。
ライトラーは、自然による目的追求をあまりにも人間に近づけて捉えているようです。まるで、人間の所業においても自然においてもただ一つの意図を貫徹することだけが問題となっているかのようです。しかしわれわれの見る限り、自然の出来事においてはたいてい、一連の目的追求はその全体が平行して進行するのであって、互いに破棄しあうことはないのです。
自然について人間的な言葉で語るとしても、自然は人間の場合なら一貫していないと呼ばれるような現れ方をする、と言わざるをえません。私としては、ライトラーは彼自身の目的論的論拠にそんな重きを置いてはならないのだと思います。
発見論的仮説として目的論を使用することには懸念があります。今目の前にしているのは調和なのか不調和なのかは、個々の事例においては決して知られません。そんなことを知ろうとするのは、部屋の壁に釘を打ち込むようなものです。継ぎ目に当たるのか、知り得ないのです。
自慰や遺精といわゆる神経衰弱の発病とつながりの問題については、私は諸君の多くと同じくシュテーケルには反対でして、以前に述べたことを、後に挙げる制限つきではありますが、維持しています。現勢神経症と精神神経症の区別を断念しなければならない理由が私にはわかりません。
前者における症状の発生は、ただ中毒症のものとしか考えられません。シュテーケル同士はここでは、心因性を実際かなり誇張しているように見受けられます。私はいまも、最初15年以上前に考えたのと同じように、次のように見えています。つまり、二つの現勢神経症、神経衰弱と不安神経症、(もしかしたら、それに並べて第三の現勢神経症として本来の心気症が加えられるべきかもしれません)は精神神経症に向けて身体側の同調をなさしめ、興奮素材を提供する。
そうするとこの素材は心的に選抜され変装されるために、一般論に言うなら、精神神経症の症状の核、真珠の中心にある砂の核、が身体側の性的発現によって形成されことになるのである。このことは無論、いまだ入念な精神分析的調査がなされていない神経衰弱に関してよりも、不安神経症やそれのヒステリーとの関係に関していっそう明白です。不安症状として表面化したりヒステリーの症状形成の核となったりするのは、不安神経症においては基本的に、諸君も何度も納得する機会を得られたことですが、放散されなかった性交興奮の一部です。
シュテーケル同士は、われわれが混沌とした神経症の内部に打ち立てた形態論的文化を棄却しすべてを一項目、例えば精神衰弱、もとに一括しようとする傾向を、精神分析外の数人の論者と共有しています。
その点でわれわれは彼にしばしば反論してきましたし、また、形態論的臨床的差異は本質的に異なったプロセスのいまだ理解されざる徴候として価値のあることがやがてわかるだろうという期待を堅持しています。
自分はいわゆる神経衰弱にも他の神経症者の場合と同じコンプレックスや葛藤をいつも見出したと、彼はわれわれを、正当に、批判しますが、この論拠はいまの争点には多分当てはまりません。同じコンプレックスや葛藤があらゆる健康者や正常者にも予測されるべきことを、われわれはとっくに知っています。
それどころか、肛門性愛や同性愛などの倒錯の蠢きの一定程度の抑圧や、幾ばくかの父親コンプレックスや母親コンプレックス、さらにそれ以外のコンプレックスの存在をいずれの文明人にも推定することに、われわれは馴染んできたのです。それはちょうど、有物体の元素分析において、炭素、酸素、水素、窒および少々の硫黄といった元素が確実に提示されると期待されるのと同じことです。有機物体を互いに区別するのは、これら元素の含有率であり、元素相互の化合物の構成です。こうして正常者であるか神経症者であるかにおいて問題となるのは、それらのコンプレックスは葛藤の存在ではなく、それらが病原的となったか否かという問いなのであり、もし病原的となったなら、それらはいかなる機制をその際用いたのか、とう問いなのです。
かつてわたしが立て今日も擁護している。現勢神経症についての学説の本質的な点は、当神経症の症状は精神神経症の症状と異なり、分析的に分解できないという、実施の検分に依拠した主張に存じています。
この主張からするなら、いわゆる神経衰弱者の便秘、頭痛、疲労は、実行的な体験に歴史的ないし象徴的に還元することができず、(場合によっては同種と思われかねない)精神神経症の症状と異なり、性的代替満足であるとか、あい対立した欲動の轟き間の妥協としては理解されません。
この場命題を、精神分析の助けを借りてうまく打ち倒すことができるとは、わたしは思いません。
それに対し、当時は信じることができませんでしたが、分析治療が間接的には現勢的症状にも治癒的影響を及ぼしうることをわたしは今日では認めています。それはつまり、分析的によって、現下の有害性により良く堪えられるようになるが、あるいは、病気の個人が性的体制の変更によってこうした現下の有害性を免れる状態になるかのいずれかのゆえです。これは確かに、われわれの療法的関心にとって望ましい展望であります。
しかし、わたしが現勢神経症の理論的問題において最終的には間違っていることが証明されたとしても、個人の立場を埒外とする知識の進歩によってわが身を慰めることが出来るでしょう。
ならば諸君は問うことでしょう。殊勝なことに自分の無謬性の必然的限界を洞察するなら、どうしてわたしはむしろ、すぐさま新たな刺戟的な提案に譲歩しないのか、どうして自分の意見に頑なに固執する老人によくよく見られる芝居を繰り返すのか、と。その答えは、自分が譲歩すべき明証性が見当たらないから、ということです。
先だつ年月においてわたしの考え方はいろいろな変化を蒙ってきましたが、それをわたしが公衆に隠諾することはありませんでした。
この変化のゆえに私は非難されましたが、今日では頑なだとして非難されることになるでしょう。こうした非難がわたしを怯えませることなどないでしょう。とはいえわたしは、自分が運命を成就しなければならないことを知っています。
運命の手を逃れることはできません。かといって運命に敵対する必要もありません。わたしは運命を待ち続けるでしょうし、その間、かねてから学んできたやり方で、われわれの科学に関わることでしょう。
諸君によって多く論じられてきた自慰の有害性の問いについては、わたしははっきりとした態度表明はしたくありません。というのも、これは、われわれの取り扱っている諸問題に対する正式のアプローチではないからです。
しかし、われわれはみな、そうせざるをえないのでしょう。世間が自慰について興味をもつのも、それ以外のことのゆえではないようです。
諸君も思い出されるでしょうが、このテーマに関する討論の最初の晩、われわれはゲストとしてこの町の傑出した小児科医をわれわれの中に迎えました。
彼はわれわれに何度も問い続けられて、何を知りたいと願ったでしょうか。それはただ、どのくらい自慰は有害であり、ある者には有害なのに、別の者にはそうでないのはなぜなのか、ということでした。してみれば、この実践的欲求に応じるよう、われわれの研究にしても求められざるをえないでしょう。
告白しますが、わたしはここでも、この問題に関してシュテーケルが果敢な正しい見解を多く表明したにも関わらず、彼と立場を共有することができません。
彼にとっては自慰の有害性とは本来ばかげた偏見であって、われわれはただ人格的に狭隘なためにこの偏見を徹底的に払いのけようとしないのだ、ということになります。
いかし思うに、われわれがこの問題を(不偏不党の立場で)それがまさにわれわれに可能な限りで、目に捉えるならば、むしろ、シュテーケルの立場への加担は神経症の病因論に関するわれわれの基本的な考え方に逆行している、言わねばなりません。
自慰は本質的には幼児の性的活動に対応し、その後には、より成熟した年月におけるこの性的活動の堅持に対応しています。神経症の源はわれわれによれば、個人の性的追求とそれ以外の(自我)性向との葛藤です。
そうすると、誰かが言いそうなことですが、わたしにとっては、こうした病因論的関係の病原要因はひたすら性欲に対する自我の反応に存することになりましょう。
そうするとその誰かは、各人はその性的追求を無制限に満足させようとしさえすれば、神経症からわが身を守ることができる、と主張するかもしれません。
見たところ恣意的であり、明らかに目的にかなってもいません。ところが、性的衝動が病原的に働きうると認めるなら、諸君としては同じ意味内容を自慰に対してももはや拒んではならないでしょう。自慰とはひたすたそういう性的欲動の轟きを実行に移すことなのですから。
確かに諸君は、自慰が病原的として責めを負わされそうなあらゆる症例において、その病原的作用をさらに、自慰のうちがに発現してくる欲動に対して向けられる抵抗に還元することでしょう。自慰は身体的にも心理的にも最終的なものではないし、本当の起動因ではありません。
そうではなく、一定の活動を表す名称にすぎません。
しかし、どれほどさらに還元されようと、病気を引き起こす原因に関する判断は、この活動に結びつけられたままですし、そしてそれは正しいことなのです。
また忘れてはなりませんが、自慰は性的活動一般と同等視されるべきではなく、性的活動だとはいえ、一定の制限条件を伴ったそれなのです。それゆえ、自慰活動のまさにこうした特殊性がその病的作用の担い手である可能性も残り続けます。
こうして、われわれは(理論的)論拠から再び臨床的観察の方を指示されることになります。そしてこの観察は、(自慰の有害な作用)という題目を削除しないよう、われわれに警告します。いずれにせよ、神経症のうちで、われわれは自慰が害をもたらした症例に関わったりします。この害、三つの異なった仕方で加えられるように思われます。
a、 未知の規制による器質的障害として。その際には、諸君がしばしば言及した、無節制や不十分な満足という観点が問題となる。
b、 心的模範という仕方によって。ただしそれは、ある大きな欲求の満足のために外界の変化が目指される必要がない限りにおいてのことである。しかるに、この模範に対する大々的な反動が展開されるときには、きわめて価値のある性格属性に向かって通路が切り開かれうる。
c、 幼児期の性目標の固着が可能となり、心的な幼稚症への遅滞が可能となることによって、そのことによって神経症に頽落する素因が与えられる。精神分析家としてわれわれは自慰の、ここで言うのは無論思春期の自慰であり、またその時期以降に継続された自慰のことです。この結果に最大の関心を寄せざるをえない。
空想とは、快原則に従った生活との間に挿入された中間領域であるが、自慰が空想というこの中間領域としてどのような意義を有しているのか、つまり、どのようにして自慰によって、なんら進歩ではなく単に有害な妥協形式にすぎない性的成長や昇華の遂行が空想のなかで可能となるのか、このことを見据えておこう。
もっともシュテーケルの需重要な証言によれば、この同じ妥協が重篤な倒錯傾向を無害化し、禁欲の最悪の結果を回避させるのだが。
性能力の持続的な衰弱は、医師としてのわたしの経験からするなら、自慰によってもたらされる一連の結末から排除することができません。もっとも、この衰弱が多数の事例において一皮向けば、単に見かけ上にすぎないことも、わたしはシュテーケルに同意します。しかし、自慰のまさにこの結末は、すぐさまそれの害に数えいれるわけにはいきません。
男性の性能力、及びそれと結びついた野蛮な積極性の一定の低下は、文化的には非常に利用価値の高いものです。この低下によって、文明人は自分に要求された性的節度や信頼の美徳を遵守することが容易になります。性能力が充溢しているなら美徳とは大抵困難な課題であることがわかるでしょう。
この主張が諸君にはシニックに聞こえるとしたら、それは決してシニシズムとして意図されているのではないことを思ってください。この主張が諸一片のドライな記述だろうとしているだけであって、それにとっては、賛意を呼び起こそうが憤慨を呼び起こそうが、どうでもよいのです。
自慰はまた他の多くのもの同様、まさに(美徳の欠落)ももてば、逆に(その欠落の美徳)もっているのです。込み入った事例の連関を一方的な実際的関心によって損害と利益に割り切って二分してしまうなら、シニシズムだとの好ましからざる風評も甘受せざるをえなくなるでしょう。
ところで、自慰による直接的障害と呼んでよいものと、(自慰という)この性的活動に対する自我の抵抗や反攻から間接的に派生してくるものとを互いに分解しておくことには利点があると思いますが、この後者の作用にわたしは今回立ち入りませんでした。
われわれに向けられた第二の厄介な問いについて、必要最低限のことを二、三さらに述べておきたいと思います。この問いは、いつ性的活動が一般に個人にとって病原的になるのかという、もう一つのより包括的な問いと部分的に重なるからです。
この部分を取り去るなら、残るは、自慰が性的満足の特殊なあり方を表す限りで、病原として実行的な多重的契機の量的要因や共同作業の影響力を検討するのが肝要でしょうが、しかしなによりもまず、個人のいわゆる生来の素因に大きな重要性を容認しなければならないでしょう。けれども、素直に言えば、生来の素因をテーマに取り扱うのは、あまり誉められたことではありません。われわれは常々個人の素因をあとになってから推論するものだからです。
事後的に、その人物がもう発症したあとに、その人にあれやこれやの素因を帰すのです。
素因をあらかじめ言い当てる術を、われわれは手にしていません。ヴィクトール.ユゴーの小説に出て来るスコットランド王のような振る舞いをわれわれはするのです。
王は、魔女を突き止める間違いのない術を誇っていました。被疑者を熱湯で焚き上げ、そのスープを玩味するのです。その味加減にしたがって王は、そのとおり、これは魔女だ、とか、違う、魔女ではない、と判定しました。
さらにもう一つのテーマにも注意を向けてほしいと思います。これはわれわれの論述では取扱われることがあまりにも少なかったものですが、いわゆる無意識的自慰のテーマです。わたしの意味するのは、終身中や、異常状態や発作の際の自慰のことです。
諸君も思い出されることでしょうが、どれだけ多数のヒステリーの発作が自慰行為を、個人がこの種の満足を断念したあとで、密かに知られることなく再び持ちきたらすことでしょうか。
また、強迫神経症のどれだけ多数の症状が、この種のかつて禁じられた性的活動を埋め合わせ、反復しようとすることでしょうか。
さらに、自慰の回帰が治療作用を及ぼすと述べることもできます。諸君の幾人かはすでにわたしと同様、患者が意図的に自慰という幼児的段階に持続的に留まろうとしているわけでもないのに、治療中に再び自慰を敢行するようになると、それが大きな進歩を意味するという経験をなさったことでしょう。
その際、諸君に喚起してよいことかと思いますが、まさにもっとも重篤な神経症患者のかなりの数の者が、自分で想起できる範囲の時期には自慰を避けていたのに、忘れられた早期の時期には自慰というこの性的活動に決して無縁でなかったことが精神分析によって証明されるのです。
とはいえ、思うに、これで打ち切りにしましょう。われわれは、自慰というテーマはおよそ汲み尽しがたいという判断においては全員一致しているのですから。